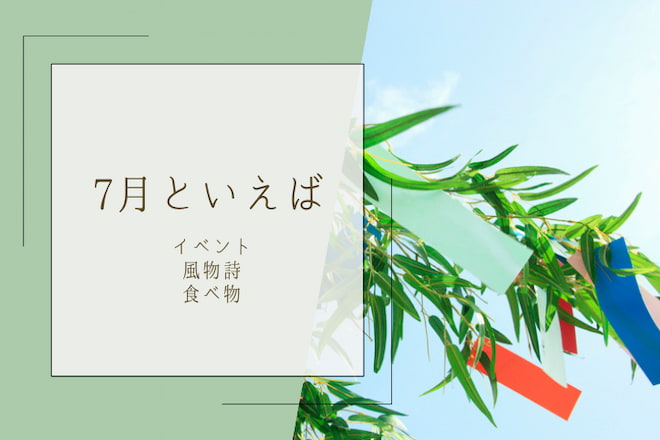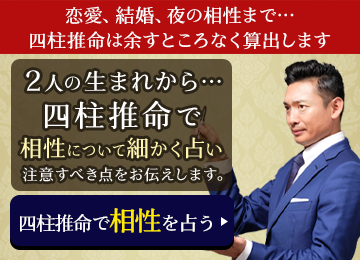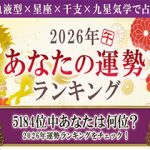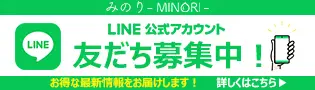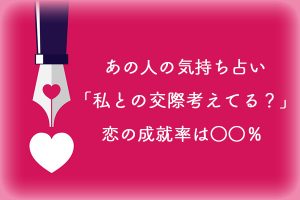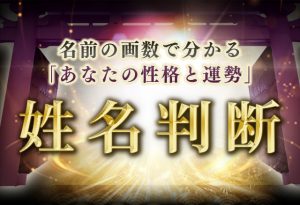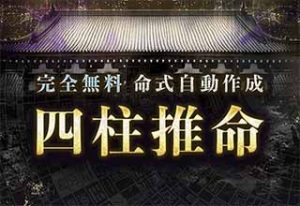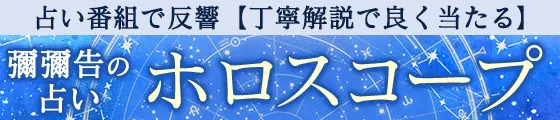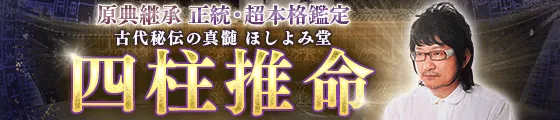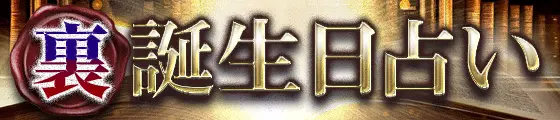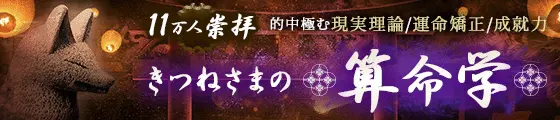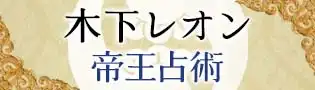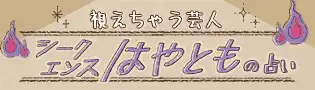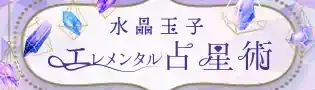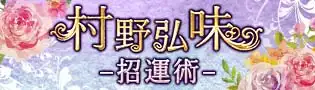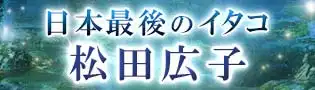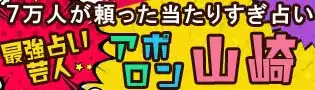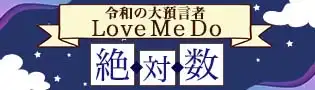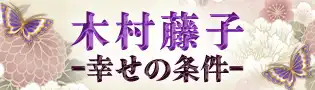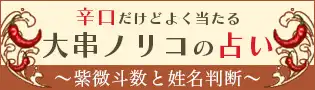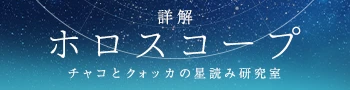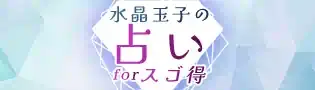七夕(たなばた/しちばた)とは、毎年7月7日、織姫と彦星が年に一度会うことができる日のこと。この日は短冊が飾ったり、天の川を眺めたりして過ごすのが昔ながらの風習です。
有名な行事ではありますが、何をして過ごしたらいいのか詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、改めて七夕の由来や短冊の意味についておさらいしていくとともに、願いが叶いやすくなる方法についてもご紹介していきます!
目次 [非表示]
七夕の名前や風習の由来は諸説あります。それでは説をそれぞれ見てみましょう。
- 棚機
- 織姫と彦星
- 乞巧奠
棚機とは、神事などに使う高貴な布や着物を織る道具のことです。神事ではおもに手芸や裁縫の上達、秋にかけての収穫を願うものなど様々な意味がこめられ、文字は違いますが読み方だけ受け継がれたものという説があります。
織姫と彦星は、元々働き者であったのにもかかわらず、結ばれた途端に怠惰になり、天帝の怒りに触れて離れ離れになってしまいます。ただ年に一度だけ、天の川を渡って会うことを許されていて、その日が7月7日の七夕であったといわれています。
徐々に機織りだけでなく、詩や手芸など芸術全般の上達を願うようになり、これが、今の笹飾りに短冊を吊るして願い事をする風習に繋がったと言われています。
七夕が日本に伝わったのは、平安時代。宮中行事として七夕がとり行われるようになり、和歌を詠んだり食べ物を備えたりして楽しんだとされています。庶民に伝わったのは江戸時代。七夕が節句の一つとなり、徐々に今の形になっていったといわれています。

- 五色の短冊
- 綱飾り
- くずかご
- 吹き流し
- 折り鶴
それでは、色別に短冊の意味や効果を見てみましょう。
「紫/黒」は「学業」に関する願い事に良いとされています。勉強や資格取得などの試験を控えている人におすすめです。五色には黒が元々含まれていますが、縁起が悪いため紫に書くようになったとされています。
「赤」の短冊は、先祖に感謝するような願い事が望ましいとされています。「いつもありがとう」「元気でいてね」など家族の健康を願うと良いでしょう。
「黄」の短冊は、人間関係に関する願い事が好ましいとされています。「新天地で友人に恵まれますように」「気の合う人と出会えますように」など。また、ご家庭がある方には家庭・夫婦円満を祈願すると効果的です。
「青/緑」の短冊には、「成長」に関わる願い事が好ましいとされています。「〇〇できますように」「〇〇な部分を直せますように」といった自身の短所や欠点を改めたい旨の内容がいいでしょう。ちなみに、昔は緑色のことを青色と呼んでいたことから、現代でも青の代わりに緑を使うようになったとされています。
「白」の短冊は、自身を律するための規則や義務に関することを書くと叶いやすいとされています。「寝坊や遅刻をしない」「皆勤を目指す」など生活態度を改善したい方は白を選んでみて下さいね。

せっかく短冊に願いを書くのであれば、叶う可能性を少しでも高めたいところ。ここでは、願い事が叶いやすくなる方法について紹介します。
- 断定形で書く
- 期限を決める
- 感謝する
ここでは、七夕の日によく食べられる行事食について、いくつか紹介していきます。
- そうめん
- 索餅
- 寿司
次に、スピリチュアル的なところから七夕について見ていきましょう。由来でもあったように、七夕は引き離された織姫と彦星が再開する特別な日。ですので、もし願い事をするのであれば、「恋愛に関する願い事」がオススメです。
特に、恋愛の中でも、「新しい出会いに恵まれますように」やすでに恋人や決まった相手がいるのであれば、「その人との仲が深まるように」といった願いをするといいですよ。
さらに、恋愛以外の願い事をするのであれば、七夕の日というのは「自分の役割や天命に気づく日」ともされていますので、仕事や人生における目標を掲げてみたり、計画を立てるのに適した時期といえるでしょう。
いかがだったでしょうか。『七夕』について、由来や願いの叶え方に至るまで色々とお伝えしてきました。地域などによっては、慣習や伝統が少しずつ異なる場合もあるでしょう。
違いを楽しみながら、また自分自身の新しい習慣の一つとして生活に取り入れてみるのもいいかもしれませんね。良い七夕の日をお過ごしください。