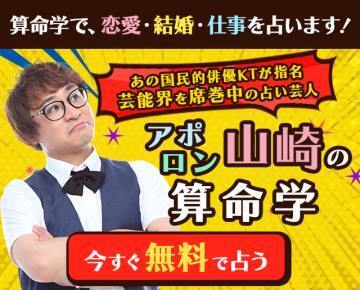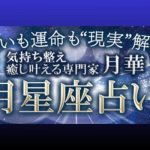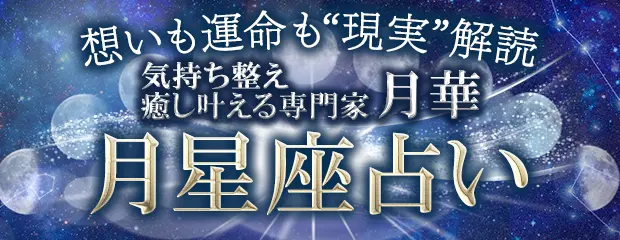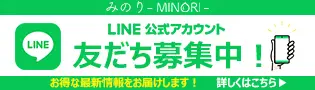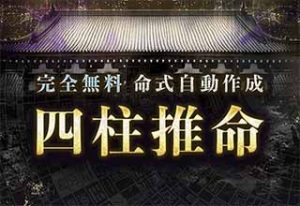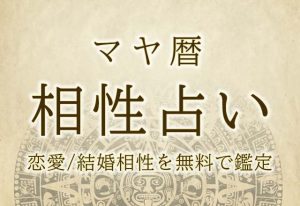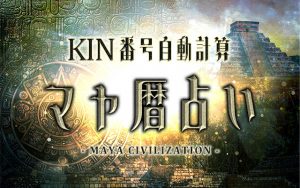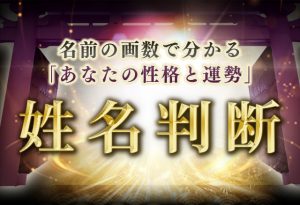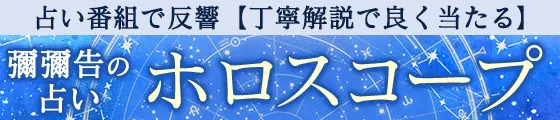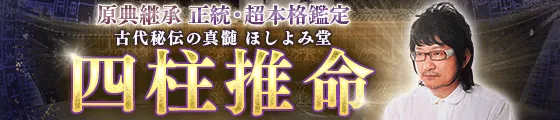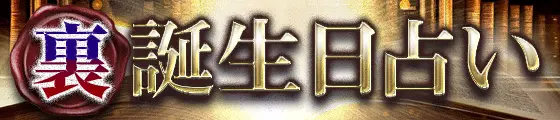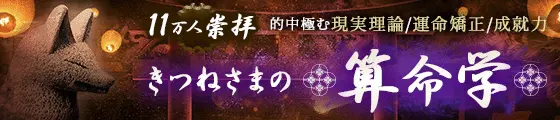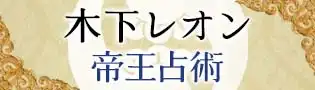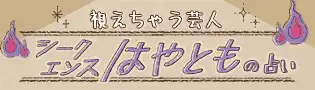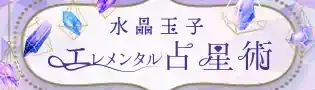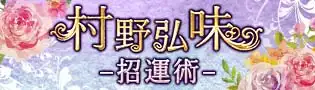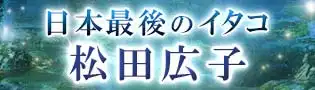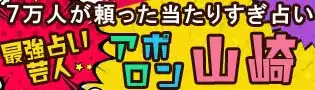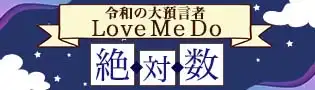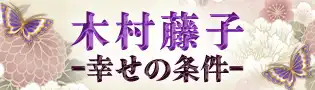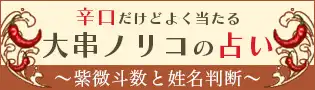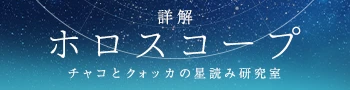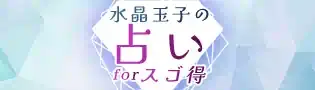「五十路(いそじ)」とは、50歳、50個、50番目を意味する言葉。三十路(みそじ)と同じ種類の言葉で、一般的亥には年齢を指すときに使われます。
「ごじゅうろ」と読みたくなりますが、それは間違い。正しくは「五」と「十路(そじ)」で「いそじ」と読みます。
それでは五十路についてと、その他日本の年齢を表わす言葉について詳しく見ていきましょう!
五十路の使い方
それでは五十路の使い方を見ていきましょう。五十路は年齢を表わす以外にも使われる言葉なので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。
- 年齢が50歳であること
- 個数が50個であること
- 順番が50番目であること
「五十路は過ぎているだろうに、とても若々しい。」
「五十路の苦難を超えて、ここまでたどり着いた。」
「次は五十路の柱を倒せ。」
五十路と他の読み方
五十路や三十路の他にも、10歳から90歳まで「数字」+「十路」で年齢を表すことができます。それぞれの読み方は以下の通りです。
| 20歳 | 二十路(ふたそじ) |
| 30歳 | 三十路(みそじ) |
| 40歳 | 四十路(よそじ) |
| 50歳 | 五十路(いそじ) |
| 60歳 | 六十路(むそじ) |
| 70歳 | 七十路(ななそじ) |
| 80歳 | 八十路(やそじ) |
| 90歳 | 九十路(ここのそじ) |
五十路の関連用語|還暦とは?
還暦とは、60歳を迎えたことをお祝いするときに使う言葉です。
日本には、「七五三」「成人」「還暦」など一定の年齢を迎えたときに使う言葉が複数あります。これらと五十路は種類が異なり、「十路」は数える単位のことで、「還暦」などは一定の年齢を迎えたことを祝う言葉です。
還暦の先の長寿祝いのときに使う言葉は以下の通りです。
- 還暦(かんれき)
- 古希(こき)
- 喜寿(きじゅ)
- 傘寿(さんじゅ)
- 米寿(べいじゅ)
- 卒寿(そつじゅ)
- 白寿(はくじゅ)
- 百寿(ももじゅ)
- 茶寿(ちゃじゅ)
- 皇寿(こうじゅ)
- 頑寿(がんじゅ)
- 大還暦(だいかんれき)
61歳(満60歳)のお祝い。長寿祝いの色は、赤と朱。
60年で十干十二支(じっかんじゅうにし)が一巡してもとの暦に還ることから、還暦と呼びます。
70歳のお祝い。長寿祝いの色は紫。
中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」が由来です。
77歳のお祝い。長寿祝いの色は紫。
喜の草書を楷書にすると「㐂」と書き、字を分解すると七が複数あるような文字となることが由来です。
80歳のお祝い。長寿祝いの色は金茶。
傘の字の略字「仐」を分解すると八十となることから傘寿と言います。また80歳のお祝いは、八十寿(やそじゅ)とも言います。
88歳のお祝い。長寿祝いの色は金茶。
米の字を分解すると八十八となることから米寿と言います。
90歳のお祝い。長寿祝いの色は白。
卒の字の略字「卆」が九十と読めることから卒寿と言います。
99歳のお祝い。長寿祝いの色は白。
百の字から一を引くと「白」になることから白寿と言います。
100歳のお祝い。長寿祝いの色は桃色。
ひゃくじゅ、紀寿(きじゅ)とも。紀とは1世紀を表しています。
108歳のお祝い。長寿祝いの色は特に決められていない。
茶の字を分解すると八十八、十、十となります。88+10+10=108となることから茶寿と言います。
111歳のお祝い。長寿祝いの色は特に決められていない。
皇の字を分解すると白、一、十、一となります。白は99歳を表します。99+1+10+1=111になることから皇寿と言います。
119歳のお祝い。長寿祝いの色は特に決められていない。
頑の字を分解すると二、八、百、一、八となります。2+8+100+1+8=119になることから頑寿と言います。
120歳のお祝い。長寿祝いの色は特に決められていない。
二回目の還暦のことを言います。
五十路の関連用語|御年とは?

御年(おんとし)とは、高齢の方に対して敬意を示して年齢をいうときに用いられる言葉です。例えば「ご職業」の「ご」のようなものです。
この言葉は尊敬の念をこめたものでありますが、御年とつけることに不満を感じる人もいます。年齢を協調されてしまうことや、御年をつけると老けている印象があることから、御年をつけると失礼なのでは?と思うようです。
三十路と呼ばれてあまりいい気がしないように、どの年齢になっても歳を協調されるのは良い気がしないものなのかもしれません。使い方には気を付けましょう。
その他年齢を表す言葉
日本語にはまだまだ年齢を表わす言葉があります。それでは一つずつ紹介していきますね!
- 辻髪(つじかみ)
- 志学(しがく)
- 二十歳(はたち)
- 弱冠(じゃっかん)
- 壮年(そうねん)
- 壮室(そうしつ)
- 而立(じりつ)
- 初老(しょろう)
- 不惑(ふわく)
- 桑年(そうねん)
- 中老(ちゅうろう)
- 知命(ちめい)
- 耳順(じじゅん)
- 華寿(かじゅ)・華甲(かこう)・華年(かねん)
- 従心(じゅうしん)
10歳のこと。
昔の髪型(つむじのあたりを丸く残した髪型)の見た目が由来です。
15歳のこと。
男子に使う言葉で、論語の「吾十有五にして学に志す」(15歳のときに学問で身を立てようと決心した)が由来です。
20歳のこと。
古代中国では20歳のことを弱と呼び、成人した証として冠をつけたことが由来です。
30~50代前半のこと。
血気盛んで働き盛りの頃という意味があります。
30歳のこと。
男性に使う言葉で、「室」(部屋)に妻がいることを表しています。
30歳のこと。
男性に使う言葉で、論語の「三十にして立つ」が由来です。
40歳のこと。
最初の長寿の祝いは40歳とされています。
40歳のこと。
論語の「四十にして惑わず」が由来です。
48歳のこと。
桑の古い漢字「桒」を分解すると4つの十と八になります。すべて合わせると48になることから桑年と言います。
50歳のこと。
50歳のこと。
論語の「五十にして天命を知る」が由来です。
60歳のこと。
論語の「六十にして耳順(まつら)ふ」(相手の言うことから善悪を判断できるようになる)が由来です。
61歳(満60歳)のこと。
華を分解すると一と6つの十が見つけられます。すべてあわせて61になることから華寿と言います。
70歳のこと。
論語の「七十にして心の欲する所に従ってわくをこえず」(自分の心のままに行動しても人道を踏み外すことがなくなった)が由来です。
まとめ
五十路、還暦、米寿など、日本にはたくさん年齢を表す言葉が存在します。それは生き続けられることのありがたさをかみしめるためです。年齢を強調されるのはあまりいい気分がするものではありませんが、生きていられることに感謝するこころは忘れずに持ち続けていたいですね。