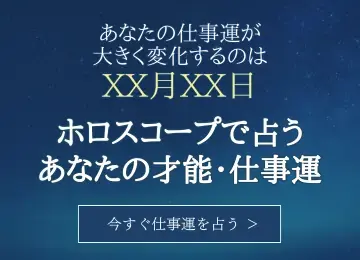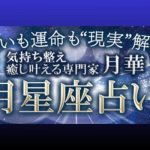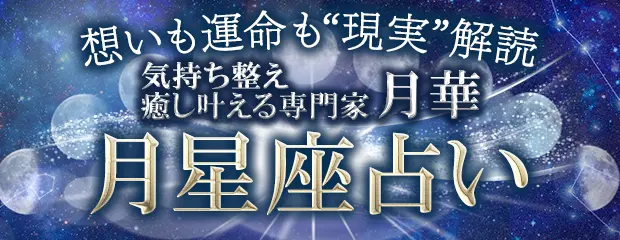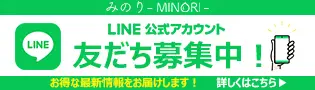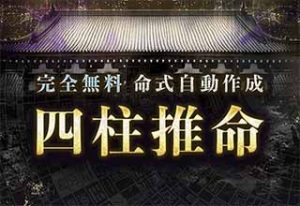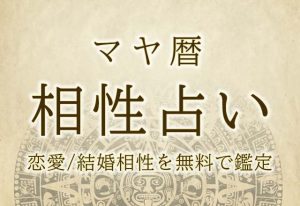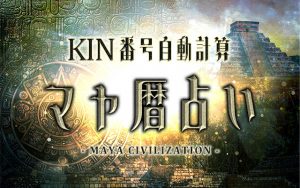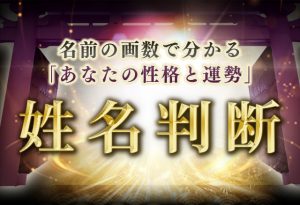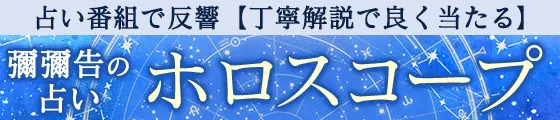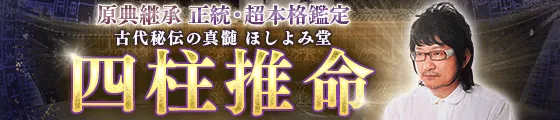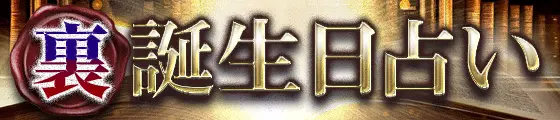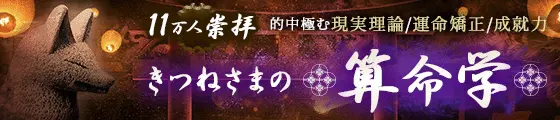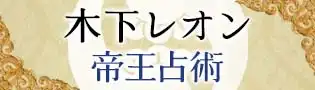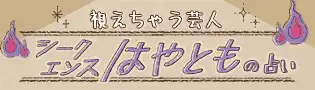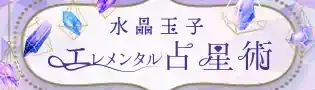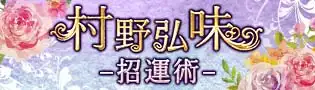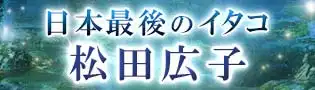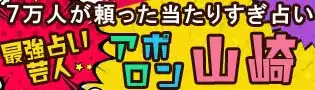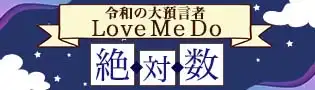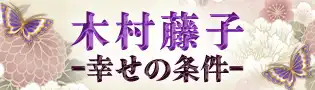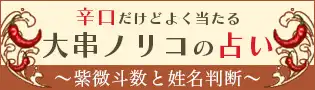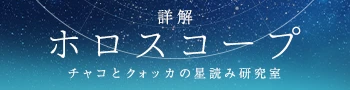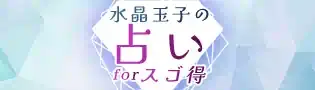「敵に塩を送る」の意味とは?
「敵に塩を送る」とは、苦境に立たされている敵やライバルを助けるという意味のことわざです。
戦国時代、敵が塩不足で困っているときに塩を差し出して助けたという史話からできた言葉とされています。
「敵に塩を送る」は、使う場面によって意味が変わります。例えばビジネスでは、ライバルに情をかけてメリットを得ることを指し、スポーツではスポーツマン精神を表す言葉となります。あらゆる場面で登場するこの言葉の意味、しっかり押さえておきたいですよね。
ということで今回は「敵に塩を送る」の由来や正しい使い方について説明していますので、詳しく見ていきましょう。
戦国時代、敵が塩不足で困っているときに塩を差し出して助けたという史話からできた言葉とされています。
「敵に塩を送る」は、使う場面によって意味が変わります。例えばビジネスでは、ライバルに情をかけてメリットを得ることを指し、スポーツではスポーツマン精神を表す言葉となります。あらゆる場面で登場するこの言葉の意味、しっかり押さえておきたいですよね。
ということで今回は「敵に塩を送る」の由来や正しい使い方について説明していますので、詳しく見ていきましょう。
目次 [非表示]
「敵に塩を送る」の由来

- 「敵に塩を送る」の元となった逸話
- 無償で塩を送ったわけではない
「敵に塩を送る」は『謙信公御年譜』や『武田三代軍記』に記されている逸話によりできたものといわれています。
戦国時代までさかのぼります。
現在の山梨県にあたる地域をおさめていた武田信玄は、海に面した地域ではないことから塩を他国から輸入していました。
ところが、軍事的戦略として、東海をおさめる今川氏真(いまがわ うじざね)と関東をおさめる北条氏康(ほうじょう うじやす)によって塩の販売を止められてしまいます。
ここで助け舟を出したのが、越後をおさめる上杉謙信です。
上杉は武田のライバルではありましたが「武力で戦っているため、米や塩など物流の面では競う気はない。塩の販売を通常通り行うため、越後から輸入しても構わない。値段を釣り上げないように商人にも命ずる。」という旨の文を送ったといいます。
これが「敵に塩を送る」の由来です。
純粋に武力で戦っているからこそ、フェアな環境でなければならないという上杉謙信の武将としての心意気を伺えるお話ですね。
戦国時代までさかのぼります。
現在の山梨県にあたる地域をおさめていた武田信玄は、海に面した地域ではないことから塩を他国から輸入していました。
ところが、軍事的戦略として、東海をおさめる今川氏真(いまがわ うじざね)と関東をおさめる北条氏康(ほうじょう うじやす)によって塩の販売を止められてしまいます。
ここで助け舟を出したのが、越後をおさめる上杉謙信です。
上杉は武田のライバルではありましたが「武力で戦っているため、米や塩など物流の面では競う気はない。塩の販売を通常通り行うため、越後から輸入しても構わない。値段を釣り上げないように商人にも命ずる。」という旨の文を送ったといいます。
これが「敵に塩を送る」の由来です。
純粋に武力で戦っているからこそ、フェアな環境でなければならないという上杉謙信の武将としての心意気を伺えるお話ですね。
ライバルの窮地を助けたとされている上杉謙信ですが、無償で塩を送ったわけではありません。
塩の販売を他国から制限され値段を釣り上げられていたものを通常価格に戻しただけだといわれています。
ただこの行動は、武田信玄にとっては、とてもありがたい話だったはずです。そのためこの話から「敵に塩を送る」と逸話を簡潔にまとめて「敵の苦境を救う」という意味の言葉になったのもむりはないでしょう。
塩の販売を他国から制限され値段を釣り上げられていたものを通常価格に戻しただけだといわれています。
ただこの行動は、武田信玄にとっては、とてもありがたい話だったはずです。そのためこの話から「敵に塩を送る」と逸話を簡潔にまとめて「敵の苦境を救う」という意味の言葉になったのもむりはないでしょう。
「敵に塩を送る」の例文と使いどころ
「敵に塩を送る」とはどのようなシチュエーションで使う言葉なのか、具体的に見ていきましょう。
- ビジネスでの例文
- スポーツでの例文
- 政治での例文
- 日常での例文
「ライバルの提案を取り入れるのは敵に塩を送ることになるが、利益が見込めるため受け入れよう」
「敵チームの物資が足りなかったため、敵に塩を送る精神で当チームの物資を提供した」
「見解が合わない相手だが、敵に塩を送って様子を見ることにした」
「気に食わない相手だが、敵に塩を送ると思って親切にしてあげた」
「敵に塩を送る」を使うときの注意点

- 親しい相手には使わない
- 純粋な優しさを表すときは使わない
「敵に塩を送る」という言葉は、友達や家族などの親しい相手には使いません。はっきりと敵やライバルだと認識した相手にのみ使う言葉です。
「敵に塩を送る」という言葉は、打算的な意味を持つ言葉です。
美談を語るときに使われることもあるが、必ずしも好意や純粋な優しさを表す言葉ではないため、誤解されないように気を付けましょう。
美談を語るときに使われることもあるが、必ずしも好意や純粋な優しさを表す言葉ではないため、誤解されないように気を付けましょう。
「敵に塩を送る」の類語
- 味方をする
- ハンデを与える
- 呉越同舟
「味方をする」ということは、相手の利益につながる行為です。そして、相手の利益になるだけでなく、こちら側にもメリットがある行為が「味方をする」です。この点がまさに、打算的な意味で使う「敵に塩を送る」の類語といえます。
「ハンデを与える」とは、スキルや知識に差が出ないように、強者に負担を課したり、弱者が有利になるようにすることをいいます。
敵に塩を送って戦いの場を整えた史話も、ある意味ではハンデを与えたことになるのかもしれません。
敵に塩を送って戦いの場を整えた史話も、ある意味ではハンデを与えたことになるのかもしれません。
呉越同舟(ごえつどうしゅう)とは、敵同士が同じ場所や境遇に居ることをいいます。昔の中国にあった仲の悪い呉と越という国でも、同じ船に乗せれば協力し合うだろうというたとえ話から来た言葉です。
敵同士でも協力し合えるという点が「敵に塩を送る」と少し似ています。ただ「敵に塩を送る」は、片方が手を差し伸べることをいうため、少し関係性が異なります。
例えば「相手の方が不利になるため”呉越同舟”になるが、物資を渡した」とは言うのは間違いです。正しくは「このままでは試合が続行できない。ここは呉越同舟、敵味方一丸となってこの状況を乗り切ろう」のように使います。
敵同士でも協力し合えるという点が「敵に塩を送る」と少し似ています。ただ「敵に塩を送る」は、片方が手を差し伸べることをいうため、少し関係性が異なります。
例えば「相手の方が不利になるため”呉越同舟”になるが、物資を渡した」とは言うのは間違いです。正しくは「このままでは試合が続行できない。ここは呉越同舟、敵味方一丸となってこの状況を乗り切ろう」のように使います。
「敵に塩を送る」の反対語
- 弱みにつけこむ
- 弱り目に祟り目
- 傷口に塩を塗る
「弱みにつけこむ」とは、ライバルの弱みを握り、相手が不利になる状況へ持ち込む様子を表す言葉です。自分が利益を得るためには競い合っている相手を蹴落とし、手段を試みないことを指します。
「弱り目に祟り目」とは、不利益を被っている状態で、さらに不幸な事態が起こることをいいます。例えば、チャレンジに失敗し、ミスを取り返そうと頑張っても裏目に出てしまうことを「弱り目に祟り目」といいます。
「傷口に塩を塗る」とは、傷口に塩を塗るとさらに痛みが増すように、不運な出来事に輪をかけて不利益が起きてしまうことをいいます。例えば失恋したとき、好きだった人が自分を振った後すぐに、別の人と付き合ったことを「傷口に塩を塗る」といいます。
まとめ
「敵に塩を送る」という言葉は、戦国時代の敵同士の関係がもととなっています。そのため、純粋な良心からの行動ではないことを示す言葉でもあります。
この言葉は、特にビジネスの場において使われるケースが多いため、正しく理解しておくきましょう。
この言葉は、特にビジネスの場において使われるケースが多いため、正しく理解しておくきましょう。
その他のおすすめコラム