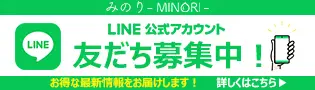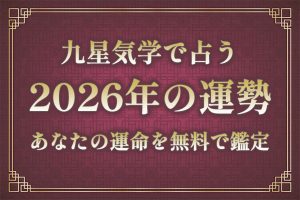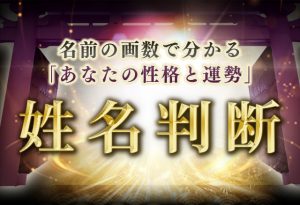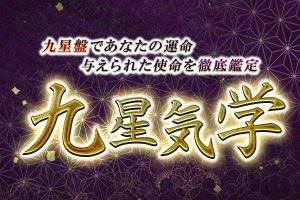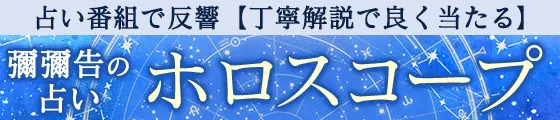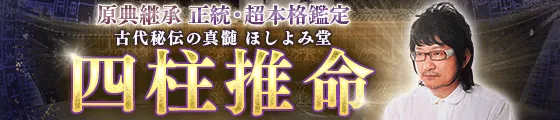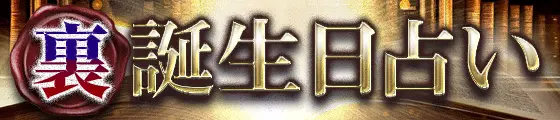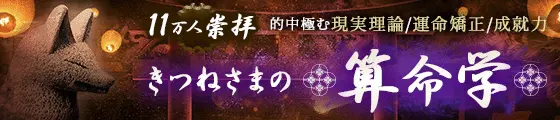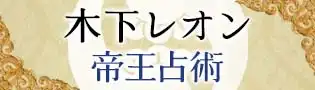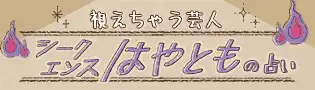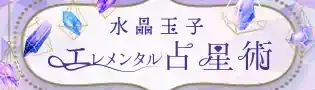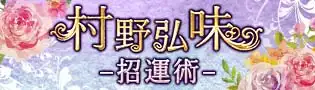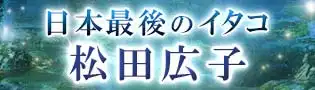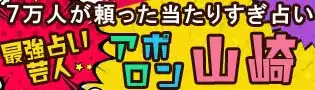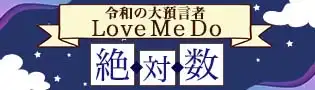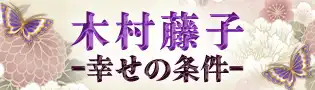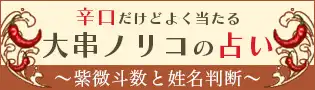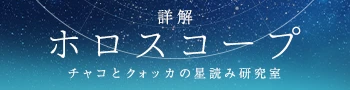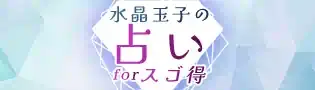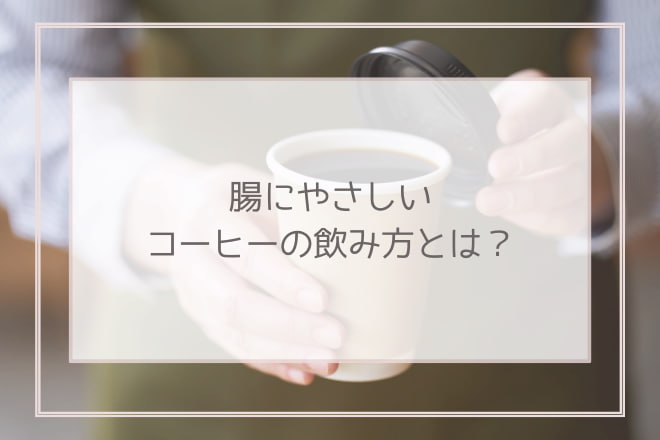
コーヒーは腸にいい?
コーヒーに含まれるカフェインは、腸の運動を活発にして便秘解消に役立つといわれています。ただカフェインは、習慣的に摂りすぎるのは良くなく、胃腸が弱っているときや疲労がたまっているときに飲むのも、あまり体には良くないことが知られています。
そこで今回は、施術1万人以上を誇る腸もみのスペシャリスト「市原香織」さんに、胃腸にやさしいコーヒーの飲み方を伺いました。

そこで今回は、施術1万人以上を誇る腸もみのスペシャリスト「市原香織」さんに、胃腸にやさしいコーヒーの飲み方を伺いました。

監修者
市原 香織
Anela
腸にやさしいコーヒーの飲み方とは?
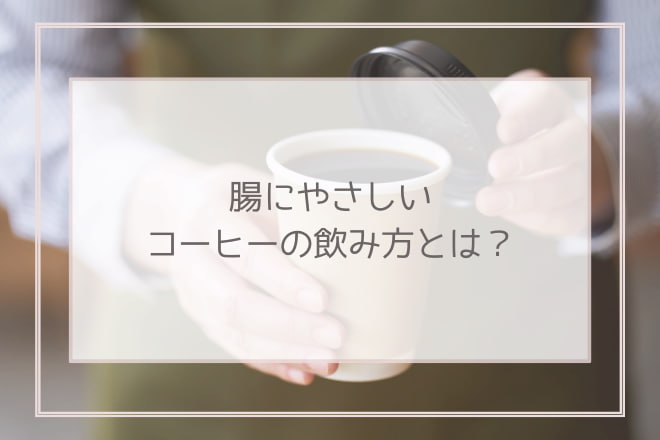
腸活向けにコーヒーを飲むなら、カフェイン少なめのものがおすすめです。カフェインは胃腸の動きを促進させると言われていますが、摂りすぎは良くなく、人によっては下痢や胃腸の不快感、水分不足になることがあります。特に身体が弱っているときに、カフェインで無理やり腸を動かすのは、控えておきましょう。
胃腸にやさしいコーヒーの種類は?
胃腸に優しいコーヒーは「デカフェコーヒー」「カフェインレスコーヒー」「カフェラテ」の3つがおすすめです。では、それぞれどんなコーヒーなのかを紹介していきます。
- デカフェコーヒー
- カフェインレスコーヒー
- カフェラテ
デカフェとは、カフェインを含む飲食物からカフェインを取り除いたもののことを指します。日本では90%以上カフェインを取り除いたものをデカフェと表示できる決まりになっています。そのためデカフェコーヒーとは、カフェインが10%以下のコーヒーということになります。
全くカフェインが入っていないということではないので、カフェインを摂りつつ、胃腸にやさしくコーヒーを楽しめます。
全くカフェインが入っていないということではないので、カフェインを摂りつつ、胃腸にやさしくコーヒーを楽しめます。
カフェインレスコーヒーは、カフェイン含有量の少ない飲食物のことです。デカフェはカフェインを取り除いたものであるのに対して、カフェインレスコーヒーはもともとカフェインが少ないもののことを指します。
カフェインの量は、豆の種類などによって変わります。カフェインレスコーヒーを飲んで胃腸に負担をかけたくないというときは、あらかじめパッケージにカフェインレスと書かれているものを選んでみましょう。
カフェインの量は、豆の種類などによって変わります。カフェインレスコーヒーを飲んで胃腸に負担をかけたくないというときは、あらかじめパッケージにカフェインレスと書かれているものを選んでみましょう。
カフェラテとは、エスプレッソコーヒーにスチームミルクを加えた飲み物のことです。ミルクが加わるのでカフェイン量はおのずと少なくなり、ミルクは胃粘膜の保護もしてくれるので、胃腸にやさしくコーヒーを飲むことができます。
ただ、動物性脂肪であるミルクを飲むと、お腹が緩くなりやすいなどの悩みが出るという「乳糖不耐性」の方もいます。そういう方は、植物性脂肪のミルクを使うのがおすすめです。植物性脂肪のミルクは腸への刺激が少なく、吸収も穏やかなので、胃腸への負担を少なくすることができます。
ただ、動物性脂肪であるミルクを飲むと、お腹が緩くなりやすいなどの悩みが出るという「乳糖不耐性」の方もいます。そういう方は、植物性脂肪のミルクを使うのがおすすめです。植物性脂肪のミルクは腸への刺激が少なく、吸収も穏やかなので、胃腸への負担を少なくすることができます。
カフェラテにおすすめ!植物性ミルク3種

カフェラテにするときにおすすめの植物性ミルクをご紹介します!
- 豆乳
- アーモンドミルク
- オーツミルク
豆乳は、大豆をすり潰したあと絞って作るミルクです。豆乳で作るカフェラテはソイラテと呼ばれることもあり、馴染みのある方も多いのではないでしょうか。大豆に含まれる体に良い成分も摂取しつつ、コカフェインも摂取できる腸活の味方です。
アーモンドミルクは、アーモンンドを水に浸して砕いてから濾して作るミルクです。食物繊維が豊富で、アーモンドの脂質にはコレステロールが含まれていません。さらにビタミンEも含まれているので、腸活をはじめとした健康に良さそうな栄養素を一度に摂取することができます。
できたばかりのアーモンドミルクには甘さがほとんどありませんが、市販のものはお砂糖が入っているものもあり甘さがあります。お家でアーモンドをミキサーにかけてミルクを作ることもできるので、お砂糖が気になる方はアーモンドから作ってみるというのも良いかもしれません。
できたばかりのアーモンドミルクには甘さがほとんどありませんが、市販のものはお砂糖が入っているものもあり甘さがあります。お家でアーモンドをミキサーにかけてミルクを作ることもできるので、お砂糖が気になる方はアーモンドから作ってみるというのも良いかもしれません。
オーツミルクは、オーツ麦(オートミール)を原料とした食物繊維が豊富なミルクです。不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方をバランスよく摂取することもできるので、腸活向きのミルクと言えます。
まれにグルテンを含むオーツミルクもあるので、アレルギーをお持ちの方は、グルテンフリー表記のものを選びましょう。
まれにグルテンを含むオーツミルクもあるので、アレルギーをお持ちの方は、グルテンフリー表記のものを選びましょう。
まとめ
腸にやさしいコーヒーの飲み方、いかがでしたか?カフェインレスコーヒーや食物性ミルクで作ったカフェラテなど、日々の生活にコーヒーが欠かせなくなっているという方も、ちょっとした工夫でできそうなものばかりでしたよね。ぜひカフェインの量やミルクの種類を変えて、腸を労わってみてくださいね!
その他のおすすめコラム