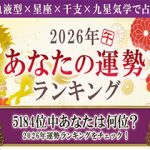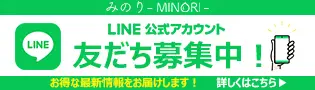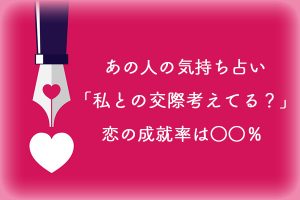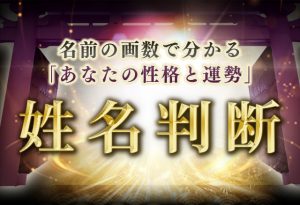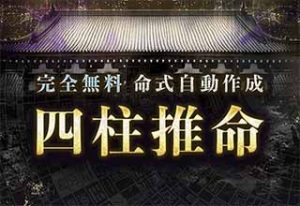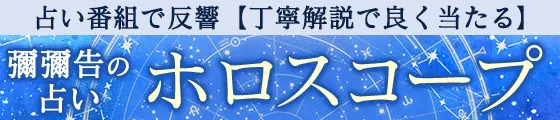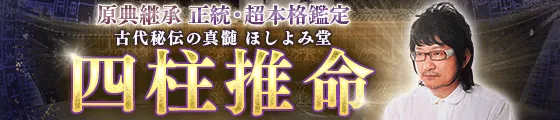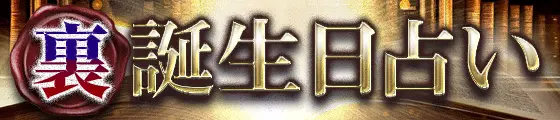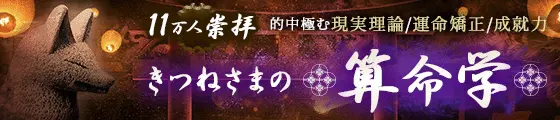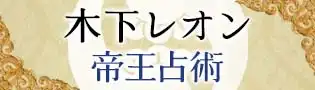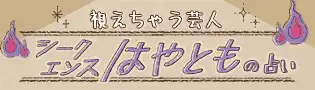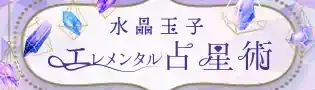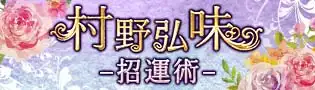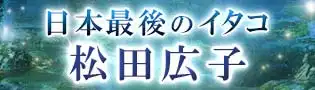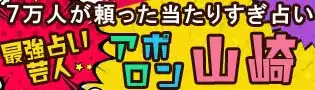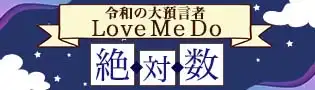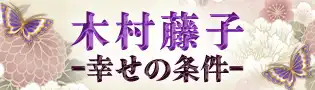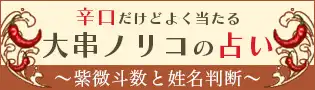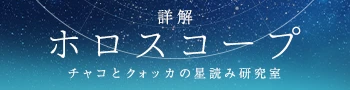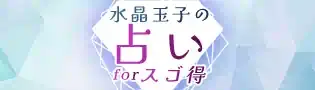土用の丑の日とは?

「土用の丑の日(どようのうしのひ)」とは、季節の変わり目である土用の期間に訪れる丑の日のことです。
「土用」とは、季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間のことをいいます。そして「丑の日」とは、立春から数えて巡ってくる干支(子・丑・寅・卯…)の二番目・丑の日のことです。そのため、土用の丑の日は年に数回訪れます。
その中でも有名なのは立秋の前7月に訪れる土用の丑の日ですよね。ということで今回は、夏の土用の丑の日についてより詳しく見ていきましょう。
土用とは?
- 納涼会・飲み会
- 納涼会・飲み会
その由来は、古代中国から伝わった五行説にあります。五行説とは、すべてのものは「木」「火」「土」「金」「水」の5つから成り立っているという思想です。五行はそれぞれ、「木=春」「火=夏」「金=秋」「水=冬」を象徴しています。そして、残りの「土」は季節の変わり目の象徴とされています。
なぜ土用と言うようになったのかというと、土用は「土旺用事(どおうようじ)」が縮まってできたと言われています。「土旺用事」とは、土が最も活発になる時期、土の作用が強まる季節、つまり季節の変わり目のことを指します。
土用の期間は、土公神(どこうしん)といわれる土を司る神が支配する期間と言われています。そのため、草むしりや庭いじり、基礎工事など土を動かす作業を避ける習慣があります。その中で、土を動かしても良いとされている日が、土用の間日と言われる日です。
土用の間日は、この日に訪れます。
| 冬土用 | 寅・卯・巳の日 |
| 春土用 | 巳・午・酉の日 |
| 夏土用 | 卯・辰・申の日 |
| 秋土用 | 未・酉・亥の日 |
土用の丑の日はいつ?
2025年の土用の丑の日は、2回訪れます。
7月19日(土)、7月31日(木)
土用の約18日間は、年によっては十二支が二順することもあるため、丑の日が2回訪れることもあります。1回目の丑の日を「一の丑」と言い、2回目の丑の日を「二の丑」と言います。
そのほかの2025年~2026年の土用の日はこちら。
| 秋土用 | 10月23日(木)~11月4日(火) |
| 冬土用 | 1月17日(土)~2月3日(火) |
| 春土用 | 4月17日(金)~5月4日(月) |
土用の丑の日には、暑い夏を乗り切るためのさまざまな風習があります。どのような風習があるのか、その中でも代表的なものをいくつかご紹介します。
- 丑湯
- きゅうり加持
- 土用の虫干し
夏の土用の丑の日には、うなぎを食べる習慣があります。
昔から続く日本ならではの風習ですが、なぜうなぎを食べるのかご存じでしょうか?では、土用の丑の日にうなぎを食べる理由を解説していきます。
- 「う」がつくから
- 栄養価が高いから

土用の丑の日に食べるのは、うなぎだけではありません。では、土用の丑の日にはどのようなものを食べるのか、一緒に見ていきましょう。
- 「う」のつくもの
- 土用たまご
- 土用シジミ
土用の丑の日には、うなぎをはじめとする「う」のつく食べ物や、古くから伝わる風習がいくつもあります。こうした伝統には、夏を元気に乗り越えるための知恵がたくさん詰まっています。
ぜひ、自分に合った風習や食べ物を取り入れて、暑い夏を健康に過ごしていきましょう。