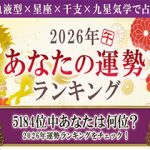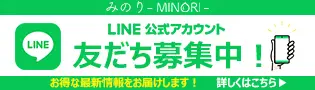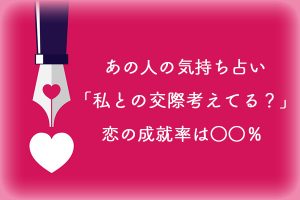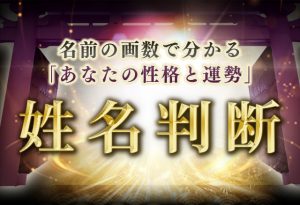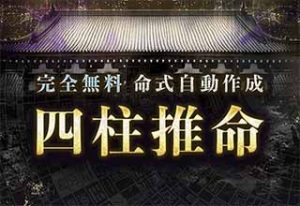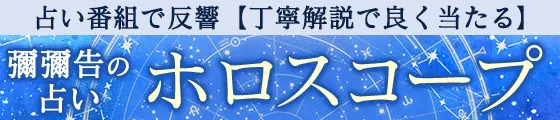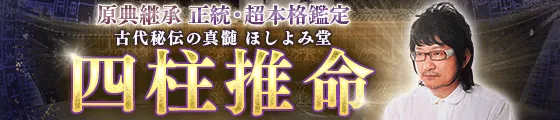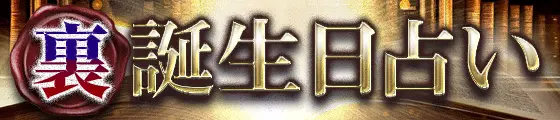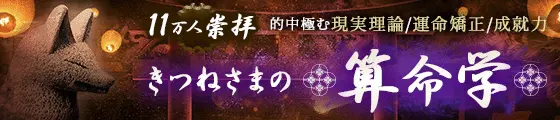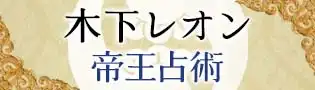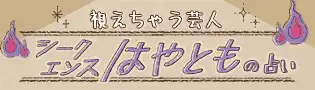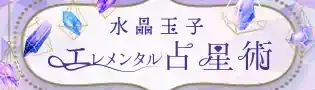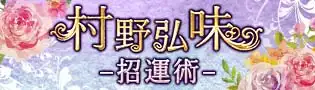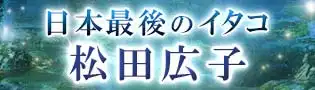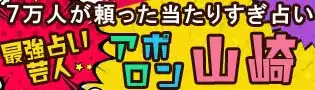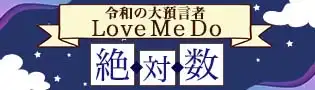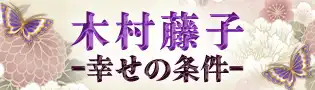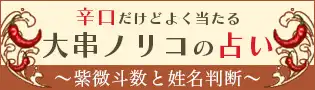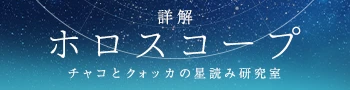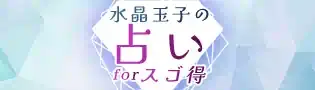暑気払いとは?

暑気払い(しょきばらい)とは、暑さを払い気力や体力を取り戻す行いことを言います。例えば暑い日に、冷たい食べ物や活力のつく食べ物を食べたり、川遊びなどをしたりすることを指します。現代では、飲み会を開くことが暑気払いの一つになっている場合が多く見られます。
今回は、暑気払いをするのにふさわしい時期や、食べるといい食べ物などについて詳しく紹介していきます。
暑気払いの由来
暑気払いは、江戸時代に始まったと言われています。暑さをしのぐために、川など涼しい場所に集まり納涼を楽しんでいたそうです。
暑気払いの「暑気」とは、体に蓄積された熱や疲労のことをいいます。語源は、漢方医学の「暑邪(しょじゃ)」という、外から来て心体に悪影響をもたらす邪気という意味の言葉から来ているといわれています。暑さという邪気を取り払って気を取り戻すという意味で、「暑気払い」と呼ばれるようになったそうです。
暑気払いをする時期は?
暑気払いをする期間は、特に決まっていません。暑さを感じる時期であれば、いつ行っても暑気払いとなります。
ただ、一般的には暑い日が連日続くようになる6月~8月に行うところが多く、暑くても5月や9月に行うことはあまりありません。
そのため、大々的に人を集めて行う暑気払いの会を開くのであれば、夏至の前後あたりから8月下旬のあたりまでで開催するのが無難でしょう。
暑気払いと納涼会の違い
納涼会とは、暑さから逃れて涼しさを味わうための会のことをいいます。主に夏の真っ盛りである7月や8月に行われ、夕涼みや夜風を楽しみながら、飲食や談笑をするのが特徴です。会社や地域の集まりとして行われることも多く、屋外でのビアガーデンや花火大会、納涼船などが人気です。
暑気払いは、暑さで弱った体の熱を冷まして、元気を取り戻す行いを指します。食事会や飲み会、冷たい食べ物や入浴、軽い運動なども含まれています。
一方で納涼会は、その暑気払いの中でも「涼を楽しむ」ことをメインにした催しです。開催時期にも違いがあり、暑気払いは初夏から残暑の時期まで幅広く使えるのに対し、納涼会は夏のピーク時に限定されるケースが多いです。
暑気払いのやり方
![]()
夏の暑さでバテ気味の体を癒すには、暑気払いが効果的です。昔ながらの風習や現代風のリフレッシュ方法など、さまざまなやり方があります。自分に合った、お気に入りの過ごし方を取り入れてみましょう。
- 納涼会・飲み会
暑い日に仲間と冷たい飲み物を楽しむのは、暑気払いの定番です。キンキンに冷えたビールやサワー、甘酒などを飲むことで、内側から体温を下げてくれますよ。また、夜風の中で行うビアガーデンなども気分転換にぴったりです。
- プール・海・川遊び
水に入ることで直接体を冷やす方法も、立派な暑気払いです。プールで泳いだり、川遊びや海水浴を楽しんだりすることで、火照った体がリセットされて、気分も晴れやかになるでしょう。
- 薬湯
薬湯とは、漢方薬や薬草などを配合した入浴剤を使ったお風呂のことです。疲労回復やリラックス効果があり、夏バテの改善にもおすすめです。
- 打ち水・風鈴
古くから伝わる知恵として、打ち水や風鈴の音も涼を呼ぶのも暑気払いの一種です。どちらも日本らしい風情を感じますよね。打ち水は日陰や夕方に行うことで、ゆっくりと水が蒸発し、体感温度を下げてくれるますよ。
暑気払いにいい食べ物
![]()
食べ物から暑さを追い払うのも、暑気払いの一つです。夏バテを防ぐ栄養素を含んだ食材を取り入れて、元気な体を維持しましょう。
- 麦でできたもの
麦は消化吸収を助け、胃腸の働きを整えてくれます。そうめんや冷や麦、冷やし中華など、小麦粉を使った麺類は食欲がない時にも食べやすいので、夏にピッタリの食べ物です。
- 瓜
きゅうりやスイカ、冬瓜、ゴーヤ、かぼちゃなど、ウリ科の野菜は体の熱を冷ます働きがあります。水分を豊富に含み、栄養価も高いので、夏にぴったりの食材です。
- 甘酒
冬のイメージが強い甘酒ですが、実は夏の季語でもあります。発酵によってビタミンやアミノ酸が豊富に含まれており、「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養価の高さが特徴です。ショウガを加えると食欲増進にもつながります。
- 酸味のあるもの
梅干し、酢の物、レモンなどの酸味のある食べ物は、唾液の分泌を促し、食欲を刺激してくれます。また酢や香辛料には、疲労回復や発汗作用もあり、夏に積極的に取り入れたい食材です。
- 氷菓子
かき氷やアイスクリーム、ゼリー、わらび餅などの冷たいお菓子も、暑気払いにおすすめです。体を一気に冷やすので、食べ過ぎには注意が必要ですが、適度に取り入れることで気分転換になるでしょう。
- 冷やし飴
冷やし飴は、麦芽水飴をお湯で溶かし、ショウガを加えて冷やした夏の飲み物です。関西地方を中心に親しまれ、ビタミンやミネラルが含まれていることから、夏バテ防止にも役立ちます。
暑気払いで使える挨拶
暑気払いの挨拶は、暑さに言及しながらも、爽やかさを感じさせるのがポイントです。ビジネスの場でもカジュアルな場でも、暑さをいたわる気持ちを込めて、手短に伝えると良いでしょう。
では、どのような暑払いの挨拶があるのか、一緒に見ていきましょう。
- 開会・乾杯の挨拶
例:みなさま、今日はお集まりいただきありがとうございます。暑い日が続いてますね。今日は、そんな暑さを吹き飛ばすような、素敵な暑気払いになればと思います。ではみなさま、乾杯!
- 閉会・締めの挨拶
例:みなさま、お楽しみのところ心苦しいのですが、お開きの時間となりました。本日はお集まりいただき、誠にありがとうございました。まだ暑さは続きますので、どうぞお身体にはお気をつけてお過ごしください。
暑気払いの関連用語
暑気払いをする時期には、季節の言葉がたくさんついています。行事や暦の区切りとして、暑気払いを行うタイミングの参考にもなりますので、関連用語を詳しく見ていきましょう!
- 夏至
夏至とは、一年のうちで最も昼の時間が長くなる日のことです。6月21日頃から7月7日頃までが夏至の時期にあたります。暑気払いの準備を始める時期に適しています。
▼小暑についてくわしく見る▼
- 夏越しの大祓
夏越しの大祓は、毎年6月30日に行われる日本の伝統行事です。半年間の厄や穢れを落とすための神事で、神社では茅の輪くぐりが行われます。
- 小暑
小暑は、7月7日頃から7月23日頃までの期間を指します。本格的な暑さが始まる頃とされており、梅雨が明ける時期とも重なるタイミングです。
▼小暑についてくわしく見る▼
- 土用
土用とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前にある約18日間の期間を指します。とくに有名なのは「土用の丑の日」で、夏の土用の期間中にあります。
- 大暑
大暑は、7月23日頃から8月7日頃までの期間です。一年のうちで最も暑さが厳しいとされる時期で、本格的な猛暑が続きます。
- 立秋
立秋は、8月7日頃から8月23日頃までの期間にあたります。暦の上では秋の始まりとされますが、実際にはまだまだ暑さが続くことが多いです。
- 処暑
処暑は、8月23日頃から9月8日頃までの時期です。この頃になると、暑さも和らぎ始め、朝晩には涼しさを感じられるようになります。
まとめ
暑気払いは、暑さを乗り切るための日本ならではの知恵や文化が詰まった行いです。食事、行事、過ごし方を工夫して、体力を回復し、気分もリフレッシュさせましょう。
暑さが厳しい季節だからこそ、自分の身体と心を大切にしながら、ぜひ暑気払いを取り入れてください。
その他のおすすめコラム