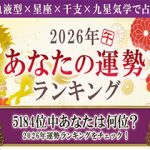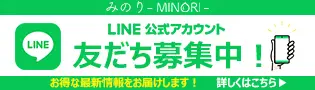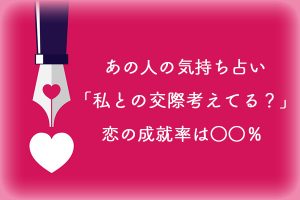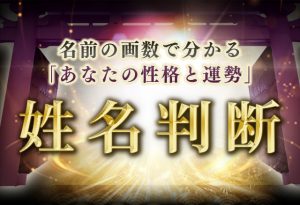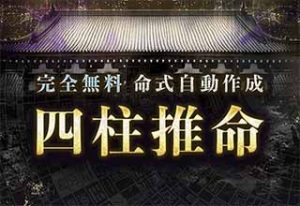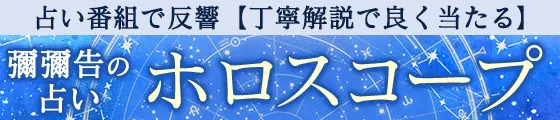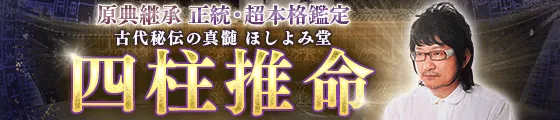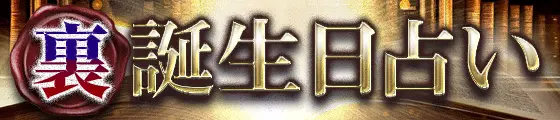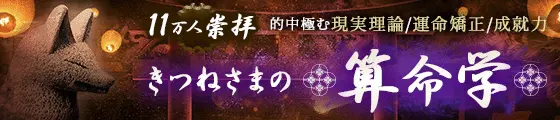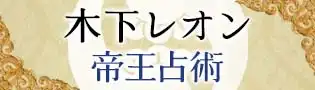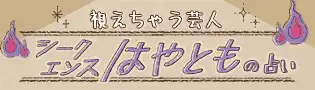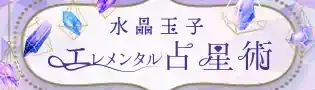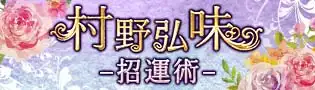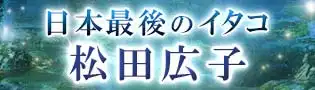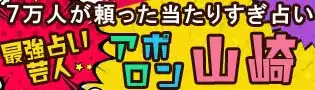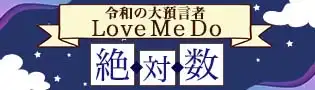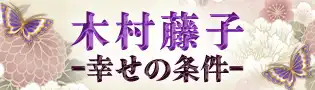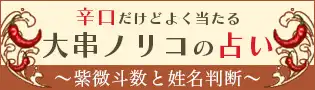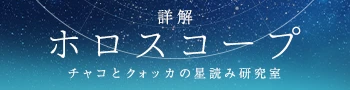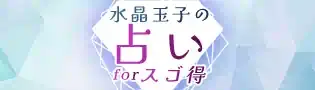今回は、二十四節気の一つ大暑について、由来や行事などを詳しく解説していきます。
今年の大暑は、ひとつ前の二十四節気・大暑から数えて約15日目の7月22日から始まり、次の二十四節気・立秋の始まる前日8月6日まで続きます。
では、大暑の七十二候を見てみましょう。
| 7/22~26頃 | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) |
| 7/27~8/1頃 | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) |
| 8/2~6頃 | 大雨時行(たいとうときどきにふる) |
- 初候
- 次候
- 末候

桐始結花
きりはじめてはなをむすぶ
7/22~26頃
桐始結花は、桐の花芽がつき始める時期を指します。桐は5月頃に花が咲き、大暑の頃には花を包む茶色くて見のような花芽がつき始めます。現代で桐はあまり馴染みのない草木かもしれませんが、かつては名家の紋章として菊と並び高貴な木として神聖視されていました。
隅田川花火大会
毎年7月の最終土曜日に行われる東京のお祭り・隅田川花火大会。起源は、江戸時代(1733年)に八代将軍・徳川吉宗が行った水神祭とされています。この水神祭は、前年の飢饉で亡くなった人たちを弔うために開かれたもので、そのために花火をあげたといわれています。

土潤溽暑
つちうるおうてむしあつし
7/27~8/1頃
土潤溽暑は、まとわりつくような熱気で蒸し暑く感じる時期を指します。むしむしとする空気は、体を疲弊させますが、夏祭りや花火大会を思い出させる空気でもあり、心躍る方もいるはず。暑さに負けず夏を楽しんで行きたいですね。
八朔
八朔とは、旧暦の八月一日のことです。八朔の「八」は8月のこと、「朔」は朔日という一日のことを意味します。古くから農家では、8月1日に、早稲の穂をお世話になっている人に感謝の気持ちとして贈る習慣がありました。この日は「田の実の節句」ともいわれていて、「田の実」と「頼み」をかけて農家に限らず感謝を伝える日に転じたとされています。

大雨時行
たいとうときどきにふる
8/2~6頃
大雨時行は、台風や夕立、集中豪雨が降りやすくなる時期を指します。いきなりの雨には驚きますし災害に発展しないにこしたことはありませんが、夏の暑さを少しだけ和らげてくれることもあるので、夏の大雨は恵みの雨でもあります。
蝉時雨
蝉時雨(せみしぐれ)とは、雨のように蝉の声があたり一面から降り注ぐ様のことです。夏の盛りは、蝉の活動が盛んになる頃です。蝉が鳴くのは、求愛行動の意味があるそうです。蝉の命は数週間から1カ月ほどだとされているので、まさにひと夏の恋、そして命がけの恋をしているのですね。
- お祭り
- 土用の丑の日
- 暑中見舞い
- 蛍狩り
- 花
- 野菜
- いきもの
- 海の幸

白粉花(おしろいばな)
他には…
青桐、含羞草(おじぎそう)、蘇鉄(そてつ)、日輪草(にちりんそう)、銀竹、百日紅

ゴーヤ

ししとうがらし
他には…
枝豆、きゅうり
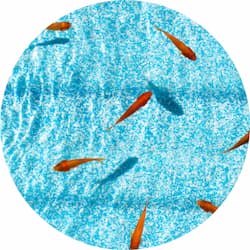
金魚
他には…
カブトムシ、水恋鳥

うに
他には…
あなご、太刀魚、アワビ